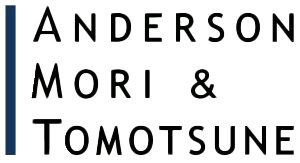(承前)
第6章 法令文のかっこ書きの訳し方
第6章では、かっこ書きで分かりにくい条文を再構成して訳す方法や、法令文に登場する訳しにくい用語の訳し方を検討する。
法人税法第57条の2
例に挙げられた法人税法第57条の2は(118ページ)、税法を専門にする者にとってはおなじみの条文であり、じつは、税法の条文の中ではとくに複雑なものではない。が、普通の方々にとっては、とんでもなくわかりにくいであろうことはよくわかる。
税法条文の読み方を解説している本などでは、著者が勧めるように、かっこ書きをいったん飛ばして骨組みだけを読み、その後各該当箇所にかっこ書きを追加していくという読み方が紹介されているのが常である。
このような条文につき、著者はかっこ書き内を注として記すことを提案しており、同感である。かっこ書きにはさまざまな役割があるので、それを見きわめることが重要である。
第7章 英語特有の問題
第7章では、英語特有で日本語には存在しない事項をどう取り扱えばよいかを検討している。いずれも考えさせられる。
shallを追放すべきか
ご承知のように、"shall"は英文の法律文書の中で、「義務」(......しなければならない)や「決めごと」(......ものとする)をおおむね表すが、それだけではないため混乱を招くおそれがある。したがって、"shall"を用いるのは「なるべく限定的にした方がよい」(136ページ)。これは局面によっていろいろな注意事項になると考えられる。
和文英訳の方向においては、和文の意味をふるい分け、義務を表す場合にのみ"shall"を用いるのがよい。なお、理論的には定義規定に"shall"を用いるべきではない(134ページ)が、現実問題としては多用されており、やむを得ない感もある。
英文和訳の方向においては、"shall"が多義的であることを心得て適切に訳し分けることである。この点につき、外国の文献に挙げられている例が紹介されているが(135ページ)、いずれも原文が誤用あるいは不適切なだけのことであり、"shall"自体の責任ではないようにも思える。
"neither party shall disclose"は"may"の意味であるとのことだが、それならば"may"を用いるべきではなかろうか。
"the corporate secretary shall be reimbursed for all expenses"は"is entitled to"の意味であるとされるが、それは受動態を前提にするからである。この文を能動態にすると、"[誰か――たとえば"the company"] shall reimburse the corporate secretary for all expenses"となり、"shall"は主語の義務を表している。なお、和文英訳方向について、「一般法律文書の英訳では、能動態で表現した方が、自然や読みやすい英文になることが多い」(82ページ)のは事実であるが、仮に原文において受動態の「主体」が明らかでない場合に、その主体を推測して主語を補って訳してよいかどうかは慎重に検討すべきである。
"if any partner shall become bankrupt"は、「条件節・仮定節(if節)中には未来形を用いない」という規範的な文法原則に照らすと、不適切な用法であると思われる。
第8章 英訳がほとんど不可能か著しく難しい日本の法律用語
第8章では、日本特有の法律用語で英訳がとくに難しいものを訳そうとするときの苦悩が語られる。法律文書を翻訳している方々においては、いずれも共感できるものばかりであろう。
ここでは、それぞれの語をどう訳すかという各論もさることながら、およそ日本特有の法律用語について、どのような問題意識を持ち、どのようなものを調べ、どのように考えるかという方法論に注目すると、他の語を検討する場合にも応用がきくと考えられる。
第9章 翻訳論又は翻訳学
第9章には、欧米の翻訳論や翻訳学と呼ばれる分野を研究した過程と得られた結論が簡潔にまとめられている。結論としては、「翻訳する目的が決定的に重要である」(173ページ)。
第10章 等価論の現在
第10章では、等価論(27ページ)をさらに追究した結果がまとめられ、結論として無益な概念であることを確認している(184ページ)。
第11章 結論
第11章には、いろいろな箇所に散在していた重要事項がキャッチフレーズとしてまとめられている。
* * *
これで、冒頭に掲げた目的を少しは達成できただろうか。実は、小文には目的がもう一つある。著者は本書が「人生最後の著書になる可能性」を示唆していらっしゃるが(まえがきiiiページ)、そうおっしゃらずに、いつまでも後進をお導きいただきたい――と申し上げたかった。
最後に、このような感謝状とも書評とも注釈とも雑談ともつかない雑文を掲載してくださった株式会社商事法務と、お読みいただいた読者の方々に感謝の意を表する。
以 上
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.