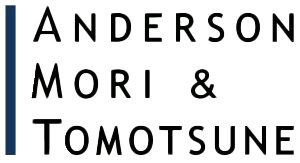- within Food, Drugs, Healthcare and Life Sciences topic(s)
- within Consumer Protection topic(s)
- with readers working within the Accounting & Consultancy industries
Ⅰ.「後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造改革のための独占禁 止法関係事例集」の公表
厚生労働省及び公正取引委員会(以下「公取委」という。)は、2025 年 2 月 17 日、「後発医薬品の安定供給等の実現に 向けた産業構造改革のための独占禁止法関係事例集」(以下「本事例集」という。)を策定しました。本事例集は、後発医 薬品の供給不安解消に向けた産業構造改革を進めるうえで問題となる私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法 律(以下「独禁法」という。)上の論点に関して、独禁法の適用及び執行に係る透明性や、事業者における予見可能性を示 すために策定されています。本事例集は、後発医薬品製造販売業者に向けて、企業結合、情報交換、品目統合、共同生産、 製造委託、共同調達、共同配送その他の企業間の連携・協力における取り組みについて、独禁法上問題とならない行為 等の具体的な事例を紹介するとともに、独禁法上の基本的な考え方を示す資料として公表されていますが、独禁法の基 本的な考え方は共通であるので、後発医薬品メーカー以外の製薬業界全体にとっても、厚生労働省及び公取委の考え方 を示す重要な参考資料であると考えられます。以下では、製薬業界全体に適用されうる内容を中心に、本事例集で示さ れている考え方を一部紹介します。
1.企業結合について
国内売上高等の一定の要件を満たす企業結合については、公取委による事前審査が必要となり、当該企業結合により 一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、企業結合が禁止される可能性があります。 競争制限の有無を検討するに際しては、まず、「市場」すなわち需要者からみた代替性によって取引の対象となる商品 や地理的範囲を画定しますが、本事例集では、医療用医薬品の市場画定(特に同一市場に含まれる商品の範囲の画定) のポイントとして、以下が挙げられています。
- 医療機関等の需要者からみて機能・効用が同種である医薬品ごとに同一の商品範囲として画定し、先発医薬 品か後発医薬品かについては問わない。
- 医薬品の分類方法として採用される ATC 分類法のレベル 3 で同一に分類される医薬品は、多くの場合、作用 部位、効能効果、作用メカニズム、用途等において共通性があるため、ATC 分類法のレベル 3 により商品範囲 が画定されることが多い。
そして、市場が画定すると、その範囲において、競争を実質的に制限することとなるかどうかが判断されます。 1 企業 結合ガイドラインの一般的な考え方に従い、市場シェアに加え、当事会社間の競争状況、供給余力、参入圧力、需要者から の競争圧力等の様々な要素を総合考慮の上競争制限の有無を判断することになります。本事例集では、後発医薬品業界 における競争制限の有無の考え方のポイントとして以下の事項を挙げています。
- 一般的には先発医薬品も含めた市場シェアの状況も考慮要素となる。
- 後発医薬品製造販売業者は、需要者から値下げ圧力を受けており、需要者は現在取引している後発医薬品製 造販売業者から、他の後発医薬品製造販売業者に切り替えることが可能であるため、通常、後発医薬品製造 販売業者に対する需要者からの競争圧力は高いと認められる。
- 企業結合により 1 社が市場シェアの過半を占めることになるとしても、当事会社以外に有力な競争者が数社 存在したり新規参入が容易であるために競争圧力が認められる場合や、企業結合により増加する市場シェア が比較的小さく競争への影響が小さい場合には、独禁法上禁止される競争制限が生じることにはならない。
2.情報交換について
独禁法第 3 条は「不当な取引制限」、すなわち、「事業者が、他の事業者と共同して、対価を決定、維持若しくは引き上 げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することに より、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限すること」(同法第 3 条第 6 項)を禁止していま す。情報交換を通じて、事業者間で、価格、数量、顧客・販路、設備等に関する合意が形成され、事業者が相互に事業活動 を拘束することによって市場における競争を実質的に制限する場合には、この「不当な取引制限」の禁止に違反します。
他方で、生産数量や製造コスト等の重要な競争手段に関する情報の交換であっても、①当該情報が正当な共同の取り 組みの検討・実施に当たって合理的に必要な範囲のものであり、かつ、②相互にその事業活動を拘束することがないよ うに必要な情報遮断措置(その検討・実施に係る関係者のみに情報を共有することや情報の目的外利用を禁止すること) が講じられる場合には、通常、独禁法上問題とならないとされています。
なお、人員等の状況から情報遮断措置を講じることが不可能な場合には、公取委への相談を活用することが勧められ ています。
3.共同調達・共同配送・製造委託等
本事例集では、共同調達・共同配送・製造委託等について、それぞれ独禁法上問題とならない行為の例が示されてい ますが、いずれも(他の要素に加えて)、①情報共有の範囲を合理的に必要な範囲に限っていること及び②情報遮断措置 を講じていることが明記されています。また、いずれの事例においても、販売活動は各社が独立して行う点も示されて います。
4.共同研究開発について
共同研究開発事例においても、情報交換については、合理的に必要な範囲に限定したうえで、当該開発の成果を踏ま えた製造販売に係る活動や各社が独自に実施する研究開発活動に関して何ら制限や情報交換を行わない場合について は、独禁法上問題とならないことが示されています。
本事例集は、これまでに公取委が示してきた考え方を踏襲するものではありますが、医療用医薬品業界における取り 組みを具体的に想定したものとなっている点で示唆的です。なお、厚生労働省は本事例集の公表にあわせて、後発品産 業の構造改革に伴う独占禁止法関係相談窓口を設置しています 2。当該窓口では、事例集に対する質問や、後発品企業 による企業又は品目間の連携・協力に関する取り組みに対する質問・相談を受け付けています。
Ⅱ.医療法等改正案の国会提出
2025 年 2 月 14 日に医療法等の一部を改正する法律案が閣議決定され、国会に提出されました。同改正は、高齢化に 伴う医療ニーズの変化や人口減少を見据えて、 ① 地域医療構想の見直しや②医師偏在是正に向けた総合的な対策を 実施するとともに、③この基盤となる医療 DX の推進のために必要な措置を講じる内容となっています。なかでも、①地 域医療構想の見直しの一つとして、オンライン診療を医療法に定義し、手続規定や施設要件を定めた点が注目に値する と考えられます。
と考えられます。 オンライン診療に関しては、無診察治療を禁止する医師法第 20 条との関係が問題となっていたところ、厚生労働省は、平成 30 年 3 月に指針 3 を公表し、オンライン診療に関して最低限遵守すべき事項を定めたうえで、これを遵守している 場合はオンライン診療が医師法第 20 条に抵触しないことを示しました。さらに、新型コロナウィルスの感染拡大を経てオ ンライン診療で行うことのできる行為を拡大してきたものの、これらはあくまで通知による法令の解釈の提示という形 で運用がなされてきました。今回の法改正で初めてオンライン診療の取扱いが法令に明記されることになります。
具体的には、まず、医療法において、オンライン診療が「医師又は歯科医師の仕様に係る電子計算機接続した電子情報 処理組織を使用し、映像及び音声の送受信により、医師又は歯科医師及び沿革の地にある患者が相手の状態を相互に 確認しながら通話することが可能な方法による診察をいう。」と定義されるとともに、オンライン診療を業として行う医 師、病院等が「オンライン診療受診施設」と定義され、オンライン診療受診施設の設置者に対して都道府県への届出義務 が課されます。また、厚生労働省令において、オンライン診療の適切な実施に関する基準(施設、人員に関する要件、体制 要件等)を定めることが規定されます。
オンライン診療に係る詳細な規制については厚生労働省令に委任されていることから、省令の内容も含め、引き続き 法改正の動向を注視する必要があります。
また、③医療 DX の推進という点では、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の改正等によ り、必要な電子カルテ情報の医療機関での共有等や、感染症発生届の電子カルテ情報共有サービス経由の提出を可能と する措置、及び医療情報の二次利用の推進のため、厚生労働大臣が保有する医療・介護関係のデータベースの仮名化情 報の利用・提供を可能とする措置などが執られることとなりました。これらについても、具体的な内容によっては医療・ 研究現場への影響が見込まれますので、細目の決定が待たれます。
Footnotes
1 企業結合ガイドライン(「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」)において、公取委が企業結合審査を行う際の考え方及びセ ーフハーバー基準(一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるとは通常考えられないものに係る基準)が明らかにさ れています。ここでの検討は、セーフハーバー基準を満たしていないことを前提としています。
2 相談希望者は、 所定の「相談申出書」を使用した上、電子メールで generic-dokkinsoudan@mhlw.go.jp まで送付する。
3 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」厚生労働省平成 30 年 3 月(令和 5 年 3 月一部改訂)
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.