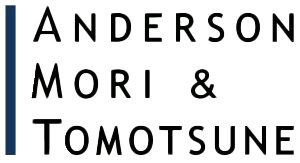- within Food, Drugs, Healthcare and Life Sciences topic(s)
- within Technology topic(s)
Ⅰ.無資格事業者による疾患リスク判定サービス等の適法性に関するガイドライン改正
厚生労働省及び経済産業省は、2025 年 3 月 28 日付で健康寿命延伸産業分野における新事業活動のガイドライン (以下「本ガイドライン」)を改正しました。本ガイドラインは、医療・介護分野と関係の深い産業において事業者ニーズ が高い事業を類型化し、基本的な法令解釈や留意事項を示しています。具体的には、(1)医師が出す運動又は栄養に関 する指導・助言に基づき、民間事業者が運動指導又は栄養指導を行うケース、(2)医療法人が、配食等を通じた病院食 の提供を行うケース、(3)簡易な検査(測定)を行うケースについて関連法令上の解釈を示していますが、特に(1)・(3)と の関係で、民間事業者が提供するサービスの医師法等との関係での適法性について解説している点が注目に値しま す。
医師法 17 条は、医師以外の者に対して「医業」 1を禁止しており、また保健師助産師看護師法 31 条は看護師以外の 者に対して診療の補助を禁止しているため、医師又は看護師ではない民間事業者が提供するサービスも医業又は診 療の補助に該当してはいけません。同条との関係で、無資格の民間事業者が提供できるサービスの範囲が問題となる ところ、本ガイドラインは以下の解釈を示しています。
(1) 医師が出す運動又は栄養に関する指導・助言に基づき、民間事業者が運動指導又は栄養指導を行うケース
まず、利用者の身体機能やバイタルデータ等に基づき、個別の疾病であるとの診断や治療法の決定等の医学 的判断を伴う行為は医師が行わなければならず、また、傷病の治療のような医学的判断及び技術を伴う運動/ 栄養指導サービスは医師又は(医師の指示の下で)看護師、理学療法士(運動指導の場合)等が行わなければなり ません。
民間事業者は、医師が民間事業者によるサービス提供を受けても問題ないと判断した者に対し、医師が診断 し、発出した運動/栄養に関する指導・助言に従い、医学的判断及び技術が伴わない範囲内で運動/栄養指導 サービスを提供することが認められます。
(3) 簡易な検査(測定)を行うケース
まず、採血等の検体採取は医行為にあたるため、民間事業者が行うことはできず、利用者自ら行う必要があ ります2 。また、民間事業者は、検査結果に基づいて、疾患のり患可能性の提示や診断等の医学的判断を行うこ とはできません。一方で、以下の事項を通知することは認められます。
- 検査(測定)結果の事実
- 検査(測定)項目の一般的な基準値
- 検査(測定)項目に係る一般的な情報
- 利用者の検査(測定)結果と、医学的・科学的根拠があり、かつ客観的で民間事業者等により恣意的に変動 させることが不可能な値を客観的に比較した結果
- 当該利用者の検査(測定)結果が、医学的・科学的根拠があり、かつ客観的で民間事業者等により恣意的に 変動させることが不可能な値に基づき設定された疾患のり患や健康状態の医学的評価に係るリスク分類 (例:A ランク・B ランク・C ランク、リスク低・リスク高)のいずれに属するかといった、リスク分類との相対的 な位置づけ
ただし、上記の通知にあたっては、利用者から見て事実や一般的な基準値・情報が示されているということ が客観的に認識可能な程度に医学的・科学的根拠が示される必要がある点には注意が必要です。特に上記項 目の最後の 2 点のような比較結果や相対的な位置付けを示す場合には、それとともに医学的・科学的根拠が実 質的に示されていない場合や、一般的な基準値といえない値に基づいている場合には、当該民間事業者によっ て検査(測定)結果に基づき疾患のり患可能性の提示や診断等の医学的判断がなされていると評価される可能 性があります。
民間事業者による検査サービスの医行為該当性について、これまでにもグレーゾーン解消制度における回答にお いて同じ方向性と解される考え方が示されていました 3 。この意味で本ガイドラインは従前の議論の方向性を踏襲す るものですが、そのような考え方が包括的に、また具体例等も合わせて確認されたことには大きな意味があると言え ます。
なお、医業該当性と医療機器該当性において必ずしも同一の判断基準を用いる論理的必然性はないと考えられま すが、プログラムの医療機器該当性に関するガイドラインでも、従前から「糖尿病のような多因子疾患の一部の因子に ついて、入力された検査結果データと特定の集団の当該因子のデータを比較し、入力された検査結果に基づき、当該 集団において当該因子について類似した検査結果を有する者の集団における当該疾患の発症リスクを提示するプロ グラム(利用者に診断との誤認を与えないものに限る。)は医療機器非該当であるが、個人を特定して、その個人の疾 病候補、疾病の発症リスクを表示するプログラムは診断に使用されることが目的と認識されるものであり、医療機器 に該当する。」と例示する等、概ね本ガイドラインで示された医業該当性とパラレルの考え方が示されています 4 。
Ⅱ.ヘルスケアスタートアップと事業会社間の連携・出資・買収のための手引書策定
経済産業省は、ヘルスケアスタートアップの更なる成長を支援する観点から、「GROWTH & EXIT PLAYBOOK-ヘルス ケアスタートアップと事業会社間の連携・出資・買収のための手引書」 5 (以下「本手引書」)を策定し、2025 年 3 月 12 日 に公表しました。本手引書は、ヘルスケア産業の成長や適切なエコシステムの構築に向けて、ヘルスケアスタートアップ と事業会社(ヘルスケアスタートアップと連携する大企業等)との間の連携・出資・買収を促進することを目的とし、そ の上で必要なヘルスケア業界に関する基本的な市場環境やビジネス領域ごとの課題について、グローバルな視点も 交えてまとめています。以下では、法務との関係で留意すべき点を紹介します。
1.ヘルスケアスタートアップのエグジット
ヘルスケアスタートアップを含め、日本におけるスタートアップ全体の傾向として、事業会社による M&A に比べて IPO(Initial Public Offering:新規株式公開)や清算が従前多かったものの、2024 年 12 月 10 日に東京証券取引所(東 証)が「グロース市場における今後の対応」と題した資料を公表し、上場基準や維持基準の引き上げ、経営者の意識改 革、M&A の促進等を通じて小規模な IPO を抑制する方針を示したため、今後、ヘルスケアスタートアップは、従来の一 般的な資金調達手段や IPO を前提とした資本政策だけではなく、補助金・助成金や融資も含めた柔軟な資金調達の選 択肢を検討するとともに、エグジットの方法が柔軟に選択できるような準備をしておく必要があります。
2.事業会社によるヘルスケアスタートアップへの出資・買収の手引
(1) 事業会社による適正評価の重要性
事業会社がヘルスケアを含むスタートアップへの出資や買収を検討する際には、出資・買収候補先を適正に 評価することが重要であり、評価にあたっては、候補先のスタートアップが参入している領域における典型的な 課題を明確にし、これまでの事業 KPI や売上などの実績に基づく企業価値評価を行うとともに、買収後の成長 にどの程度リソースを投入できるかを明確にした上で、その投入するリソースがもたらす「シナジー」や事業へ のインパクトについても、客観的かつ具体的に評価することが推奨されます。また、投資は単に買収金額で完結 するものではなく、買収後に発生する追加的なリソース投入や運営コストも含めて総合的に検討することも重 要です。
(2) PMI における課題
M&A を成功に導くためには、買収後の PMI(Post Merger Integration:M&A 後の経営統合)が重要であると ころ、この点に関しては多くの事業会社が課題を感じていることが経産省の調査で明らかになりました。PMIの 失敗要因としては、短期的な利益目標の達成を優先することで、長期的な成長や買収本来の目的が見失われる こと、買収先企業の放置、買収先企業の文化や価値観を軽視した強引な統合等が挙げられます。買収による本 来の価値の実現や目標達成のためには、統合プロセスの計画と実行が重要となります。
その他、本手引書では、ヘルスケアスタートアップの市場参入状況や資金調達状況、領域ごとに見たヘルスケアスタ ートアップが直面する壁等も紹介しています。なお、経済産業省(近畿経済産業局)は、「スタートアップの知財・法務ガ イドブック ~バイオ・ライフサイエンス領域の創業期におけるポイント~」 6も公表しています。こちらは、バイオ・ライフ サイエンス領域のスタートアップのビジネスモデルの他、知財戦略や、バイオ・ライフサイエンス領域で締結される契約 について、基礎的な事項を幅広く解説しており、こちらも新たにバイオ・ライフサイエンス領域の知財・法務に関わる方 にとっては参考となる内容となっています。
Footnotes
1 医療及び保健指導に属する行為のうち、医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為(医 行為)を業として行うこと(最判令和 2(2020)年 9 月 16 日刑集 74 巻 6 号 581 頁)
2 検体採取については、衛生検査所の登録を義務付ける臨床検査技師等に関する法律 20 条の 3 との関係性につい ても解説されています。民間事業者が人体から排出され、又は採取された検体を業として検査しようとする場合には 同条に基づき衛生検査所としての登録が必要である一方、利用者が自ら採取した検体について、診療の用に供さな い生化学的検査を行う施設において当該検査を実施する場合は衛生検査所登録が不要であるため、衛生検査所登録 をしていない民間事業者は、この限りでサービスを提供する必要があります。
3 グレーゾーン解消制度・新事業特例制度 2021 年 4 月 30 日付回答(臨床検査に用いた後の残余血液を、試験用とし て有償販売する事業)
4 「プログラムの医療機器該当性判断事例について」(2023 年 3 月 31 日厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査 管理課)
5 https://www.meti.go.jp/press/2024/03/20250312002/20250312002.html
6 https://www.kansai.meti.go.jp/2-4bio/Startup/lifescience_startup_guidebook.html
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.